作家生命って
意外と短いもんだよなぁと
思ったときに
作曲家について
調べてみていると
ひとつのブログが
検索に出てきました.
今日はそのブログを
参照しながら
今後の活動について
考えてみています.
ヒントがありそうと
思いますので
ぜひ最後まで
お読みください.
職業作曲家さんのブログを読んでギャップに気づいた話
それでは、行ってみましょう!
さて、ここのところ
少し以前の翻訳勉強会の
アーカイブをみていました.
小説の翻訳のはなしになり
どうやら小説家の方の
作家生命は10年くらいらしい
というはなしが出ていました.
なんでも20年くらいすると
入れ替わってるから
ということのようでした.
確かに作家として
ずっと書いている人もいるけど
おそらくそういう人は少数で
10年も経てば一周して
自分の手札を全て使ってしまうような
感じになるんだろうなと
思いました.
ふと作曲家の場合は
どうなんだろう?
と思ってインターネットで
検索してみると
妙に詳しい記事が
検索に引っかかりました.
こちらのブログです.
http://yoshim.cocolog-nifty.com/office/2013/03/post-51db.html
かなり詳しいことが
書かれていたので
どなたのブログだろう?
と思ったんですが
作曲家の吉松隆さんの
ブログだったようです.
(現役の作曲家さんのブログは
大変ありがたいですね.)
音楽業界とか
作曲家の生活の
厳しさがよく感じ取れるような
記事になっていました.
職業作曲家として
やっていくのであれば
こういう生活になる
ということであれば
結構燃え尽きてしまう方も
多い生活スタイルだろうなと
思いました.
実際に音大生さんとかでも
燃え尽きてしまう方が
いらっしゃるようです.
加えて生き残る人も少なく
作家として良い曲が残せる
ピークというのも数年な人も多い
という大変厳しい業界のようでした.
作曲家という視点でみると
30代、40代は若手という世界で
50代後半くらいからやっと
本格的な作家としての曲が
残るような世界のようで
私もうまく
続ける工夫をしたほうがいいなと
感じる場面が増えています.
おそらくですが
作曲家としてやっていきたいなら
体力をつけたほうがいいだろうなと
感じています.
私の場合は
受注の仕事をメインには
据えていないので
自分のペースでやっていく感じなんですが
そのやり方もまた
コツがあったりします.
無理をしないような
ルーティンの構築が
求められるような気がします.
むかしの作曲家というと
東京の裕福な家に生まれて
音大に行ってから活動しているような
人が多いイメージがありましたが
いまはインターネットやSNS
またサブスクの時代ということもあり
地方で音楽をやっていても
全然収益化はできる時代かなと思います.
私個人としては
ずっと地方にいるのではなく
東京に出てみる期間があったほうが
いいなと感じている立場なんですが
自分はそれまでの仕組みでは
自分はやっていくのは難しいと
考えたため
自分で城をたてて
やってみているところです.
作曲をやっていくゴールを
どこにすえるか?という問題は
あるのかもしれませんね.
今の私はひとまずのゴールを
作曲だけの印税収入で月20万
としています.
ここになるまでももうちょっと
紆余曲折ありそうですが
いまはチャンスのタイミングで
秋くらいにしかけていこうと
考えています.
いまはちょっと
諸々準備をしていますので
今後の動きにも
ご期待ください.
それでは、今日はこの辺で.
いつもお読みいただき
ありがとうございます.
また明日です!



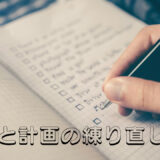
[…] 職業作曲家さんのブログを読んでギャップに気づいた話 職業作曲家さんのブログを読んでギャップに気づいた話 […]